概要
数多ある日本の伝統文化の中でも最も修道人口が多く、世界的にも広く紹介されている日本を代表する伝統文化、茶道。茶道の歴史をひもとくと、そこには意外と知られていない長い歴史が見えてきます。
元々は「茶の湯」と呼ばれていたものがいつしか茶道と呼ばれるようになり、そもそも男性がたしなんでいたものが、気づけば女性のたしなみとなった歴史的経緯。これらをひもとくことで、なぜ茶人CHABITOが今の事業を始めたのかも見えてきます。
茶の歴史
茶の輸入~初の国内栽培成功
 茶には複数の分類があり、最も大まかに分けると抹茶、煎茶、ほうじ茶、発酵茶、低発酵茶の五種類あります。抹茶や煎茶、ほうじ茶は言わずと知れた日本を代表する茶の形ですが、発酵茶や低発酵茶と言う言葉は聞き慣れないかもしれません。実は発酵茶とはプーアル茶や紅茶を指し、低発酵茶は烏龍茶を指します。
茶には複数の分類があり、最も大まかに分けると抹茶、煎茶、ほうじ茶、発酵茶、低発酵茶の五種類あります。抹茶や煎茶、ほうじ茶は言わずと知れた日本を代表する茶の形ですが、発酵茶や低発酵茶と言う言葉は聞き慣れないかもしれません。実は発酵茶とはプーアル茶や紅茶を指し、低発酵茶は烏龍茶を指します。
日本国内で最初に茶の記録が残っているのは奈良時代のこと。その当時はまだ唐(現・中国)でも抹茶法は発明されていなかったようで、団茶と呼ばれる茶葉を発酵させて団子状に固めたものが日本に輸入されていたようです。
抹茶法が成立するのは宋の時代だったと言われており、日本に抹茶が輸入され始めたのもその時期のようです。しかし日本国内で茶の栽培はなかなか上手くいかず、ようやく成功したのは1312年。元より臨済宗の教えと茶の苗木を持って帰国した栄西禅師が京の都の外れで茶の木の栽培に成功したことにより、はじめて日本国内産の茶が生まれました。
それまでは何百年もずっと茶は隋や唐、宋から輸入しており、当時の輸入品だけに極めて貴重で高額、富裕層の中でも頂点クラスの人物しか茶をたしなむことは出来ませんでした。しかし日本国内で茶の栽培に成功したことで、茶の文化は広がりを見せ始めます。
茶の湯の成立
 鎌倉後期~室町期、佐々木道誉と言う婆娑羅(派手好きの意)武将がおりました。彼は隋、唐、宋などから輸入された薬入れや薬湯を飲む器を、それぞれ茶入と茶碗に見立て、それらを用いて闘茶と呼ばれる茶会を催しました。茶の作法も唐に学んだ僧から教えてもらっており、それが現代茶道につながる原点中の原点とも言えます。
鎌倉後期~室町期、佐々木道誉と言う婆娑羅(派手好きの意)武将がおりました。彼は隋、唐、宋などから輸入された薬入れや薬湯を飲む器を、それぞれ茶入と茶碗に見立て、それらを用いて闘茶と呼ばれる茶会を催しました。茶の作法も唐に学んだ僧から教えてもらっており、それが現代茶道につながる原点中の原点とも言えます。
道誉はもてなし好きとしても知られており、当時敵対していた楠木正成が京の都に攻め入った折、負けを察した道誉は家人に膳や酒、花などを用意し敵対勢力を目一杯もてなすように申しつけました。もてなし好きの道誉が仕掛けた歌会や茶会(闘茶)は道誉らしさあふれる派手な物だったと伝わっており、現在国宝に認定されている曜変天目茶碗の艶めかしい美しさを見れば、道誉の婆娑羅趣味がうかがえます。
現代でも「唐物(からもの)」と呼ばれる輸入品の茶道具は大変珍重されており、専用の点前はおろか、唐物道具の格付けに応じて十種類以上の点前が存在するほどですが、これもまた道誉の影響であることに疑いはありません。
佗茶
 室町時代後期、京の都は戦火に包まれました。歴史の教科書にもあかるい応仁の乱です。その乱を横に見つつ、己の禅を極め一躍有名になった人物がおります。その名を一休宗純、こと「一休さん」として知られる大徳寺第48代住持です。
室町時代後期、京の都は戦火に包まれました。歴史の教科書にもあかるい応仁の乱です。その乱を横に見つつ、己の禅を極め一躍有名になった人物がおります。その名を一休宗純、こと「一休さん」として知られる大徳寺第48代住持です。
一休和尚の禅風は非常に変わっており、僧侶で有りながら勇ましい刀をたずさえ、引き抜いてみたらただの木刀で、「外見がいかに素晴らしくても中身が伴わぬ物に意味は無い」と説いたり、毎年の正月には杖のてっぺんにその辺で拾ったしゃれこうべ(頭蓋骨)を取り付け、「門松は 冥土の旅の 一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」と、正月を祝う=年を取る事の皮肉を歌いながら町中を闊歩したりもしました。 そんな一休の禅風に惚れ込み入門した1人の男、村田珠光。珠光は一休の教えに強い影響を受け、それまで道誉ら大名達が作り上げた派手好みの茶風に一石を投じるべく、応仁の乱などで割れ欠けした茶道具や、朝鮮由来の日用雑器の中にも美しさはあるものだ、と説いて回ります。これが佗茶の原点となりました。
そんな一休の禅風に惚れ込み入門した1人の男、村田珠光。珠光は一休の教えに強い影響を受け、それまで道誉ら大名達が作り上げた派手好みの茶風に一石を投じるべく、応仁の乱などで割れ欠けした茶道具や、朝鮮由来の日用雑器の中にも美しさはあるものだ、と説いて回ります。これが佗茶の原点となりました。
珠光の教えに以下のような物があります。
「さて昨今、「冷え枯れる」と申して、初心の者が備前・信楽焼などをもち、目利きが眉をひそめるような、名人ぶりを気取っているが、言語道断の沙汰である。「枯れる」ということは、良き道具をもち、その味わいを知り、心の成長に合わせ位を得、やがてたどり着く「冷えて」「痩せた」境地をいう。これこそ茶の湯の面白さなのだ。」(現代語訳 能文社 2009年)
佗茶の考え方の原点である「冷え枯れる」思想を、何よりも最もわかりやすく、そして明確に教えてくれている一文だと言えます。
佗茶の完成者
珠光が提唱した茶の価値観は、後に珠光の孫弟子にあたる武野紹鴎(たけのじょうおう)が「侘び」と言う言葉を用いることで、明確に定義されるようになりました。紹鴎は藤原定家の歌を使って「侘び」の価値観を説明します。
「見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮れ」
この歌による説明が多くの人の共感を呼び、彼らは侘び茶の世界に傾倒しはじめます。
そんななか、同じく珠光の孫弟子にあたる北向道陳の紹介で紹鴎の門をたたいた人物がおりました。その名を田中与四郎、後の千利休です。
紹鴎は与四郎の入門試験のつもりで、きれいに掃き清められた庭を指さし、「この庭をきれいにせよ」と申しつけます。すると与四郎はほうきの一つも持たずに庭へ降り、そこにあった紅葉の木をゆさゆさと揺らし、葉を落としました。庭の飛び石に舞い散る落ち葉を確かめた与四郎は、「先生、これで庭がきれいになりました」と言い、たいそう紹鴎を驚かせたと言います。この頃から既に、後に千利休と呼ばれるようになる大物の器を秘めていたのでしょう。 数十年の時は過ぎ、織田信長によって足利義昭が京の都から追放されたことにより、足利将軍家の権勢は終わりを告げます。室町時代の終わり、そして安土桃山時代の始まりです。その信長の後ろ盾となった商人の1人に、成長した田中与四郎こと千宗易がいました。
数十年の時は過ぎ、織田信長によって足利義昭が京の都から追放されたことにより、足利将軍家の権勢は終わりを告げます。室町時代の終わり、そして安土桃山時代の始まりです。その信長の後ろ盾となった商人の1人に、成長した田中与四郎こと千宗易がいました。
宗易は今井宗久・津田宗及とともに織田信長三茶頭の1人に名を連ねており、既に茶人として相当の地位を得ておりました。その当時、戦国大名の大半は茶の湯をたしなんでおり、信長に帰順した武将は三茶頭のいずれかに茶を学んでいたと言われています。後の関白・豊臣秀吉こと羽柴秀吉もまた、利休の弟子の1人でした。
堺の大商人だった今井宗久・津田宗及の両名は、当時では世界でも有数の資産家。それに対して宗易はと言うと一介の倉庫業者(今で言うところの物流業者)に過ぎず、そんな彼が信長三茶頭の1人に列席するのは、ひとえに信長の考えた実力主義の賜物だったと言えます。そして信長がそう評するに相応しいだけの商才・才覚を、宗易は備えていたのです。
超のつく資産家二名は当然のことながら、一介の倉庫業ごときが持つ事など不可能な、現代でも重要文化財や国宝に認定されている様々な茶道具を持っていました。宗易はそんな彼らを見、自らに備わった卓越したセンスを用い、あえて粗末な道具を用いつつも他者が思いもつかない独特の茶のもてなしを展開していきます。それは数多いた茶人達を大いに驚かせ、かつ喜ばせることに成功しました。
茶事のもてなし
 そんな利休が発明したのが、茶事と呼ばれる茶会の形式です。「行事」「慶事」「弔事」などのように語尾に「事」をつけるのは、いずれも特別な儀式を意味します。「食事」と言う単語もまた、自然との調和や食材への感謝を大切にする日本人ならではの感覚からうまれたもの。利休はそれまで「茶の湯」「茶の会(ちゃのえ)」と呼ばれていたものを改め、そこに禅僧の食事形式をアレンジしたものを取り込み、懐石料理が付属した茶会こと「茶事」を提唱します。これは弊社の茶事の原点的存在でもあります。
そんな利休が発明したのが、茶事と呼ばれる茶会の形式です。「行事」「慶事」「弔事」などのように語尾に「事」をつけるのは、いずれも特別な儀式を意味します。「食事」と言う単語もまた、自然との調和や食材への感謝を大切にする日本人ならではの感覚からうまれたもの。利休はそれまで「茶の湯」「茶の会(ちゃのえ)」と呼ばれていたものを改め、そこに禅僧の食事形式をアレンジしたものを取り込み、懐石料理が付属した茶会こと「茶事」を提唱します。これは弊社の茶事の原点的存在でもあります。
信長の死後、羽柴秀吉あらため豊臣秀吉が成立したことにより、秀吉の師匠だった宗易が、豊臣政権唯一の茶頭として台頭します。秀吉は信長にならい名物茶道具を敵対大名との取引道具に用いたり、配下の武将への褒美として茶道具を進呈したり、はたまた功績を挙げた武将には利休への入門を許可するなどし、茶の湯と茶道具を政治利用しました。これを秀吉は「御茶之湯御政道」と呼び、これにより天下の茶風はいったん利休流に統一されることとなります。
ただ利休流に統一されたからと言うだけでなく、利休による茶事のもてなしは多くの戦国大名や町人達の心を見事につかみ、利休の名は遠く奥州伊達藩にまで鳴り響きます。伊達政宗は利休最後の弟子とも言われておりますが、仙台から京都は伏見まで一ヶ月以上の時間をかけてわざわざ利休の手ほどきを受けに来るほどに、利休のもてなしは群を抜いていたのでしょう。正宗のみならず、利休の弟子は大名だけで200人を遙かに超えていたとされています。
千利休の誕生
 宗易が利休と言う名をいただく直接的なきっかけとなったのは、正親町天皇への献茶でした。宗易は地位からすれば一介の民間人だったために天皇に直接謁見することは出来ません。そこで考えられたのが、宗易に居士号を与えて僧侶と言う立ち位置にすることで、天皇への謁見が出来るようにする、と言う策です。これにより千宗易ははれて千利休へと名を変えることになります。
宗易が利休と言う名をいただく直接的なきっかけとなったのは、正親町天皇への献茶でした。宗易は地位からすれば一介の民間人だったために天皇に直接謁見することは出来ません。そこで考えられたのが、宗易に居士号を与えて僧侶と言う立ち位置にすることで、天皇への謁見が出来るようにする、と言う策です。これにより千宗易ははれて千利休へと名を変えることになります。
そんな利休を慕う武将は極めて多く、利休賜死のおりには豊臣政権に対するクーデターが企てられ、一触即発になったほどでもありました。それほどまでに利休の影響力は大きく、「侘び茶」と言う絶対的価値観は現代茶道にも引き継がれ、茶道の基準はおろか、日本人の美的感覚を支え続けております。
流派茶道の成立
 利休の死後、いったんお家断絶となった千家は、利休を慕っていた多くの大名達による嘆願が功を奏して再興されました。千家三代目となる宗旦には息子が複数おり、その中でも次男・宗守、三男・宗左、四男・宗室の三名が利休~宗旦に伝わる茶の湯を引き継ぎ、それぞれに庵を構えました。次男・宗守は今につながる武者小路千家、三男・宗左は表千家、四男・宗室は裏千家を立てることになり、これが現代の茶道三千家の原型になります。
利休の死後、いったんお家断絶となった千家は、利休を慕っていた多くの大名達による嘆願が功を奏して再興されました。千家三代目となる宗旦には息子が複数おり、その中でも次男・宗守、三男・宗左、四男・宗室の三名が利休~宗旦に伝わる茶の湯を引き継ぎ、それぞれに庵を構えました。次男・宗守は今につながる武者小路千家、三男・宗左は表千家、四男・宗室は裏千家を立てることになり、これが現代の茶道三千家の原型になります。
その当時はまだ流派茶道らしい風潮は生まれておりませんでしたが、三千家それぞれに道具の好みが少しずつ分かれていき、本格的に家元制度が導入され流派茶道が本格的にスタートしたのは利休没後100年以上たった七代宗左・宗室・宗守のあたりだと考えられます。と言いますのも、三代宗旦の活躍により千家は再興されましたが、その頃から茶の世界は大名が中心となって楽しむ大名茶と町人が楽しむ町人茶に大別されるようになり、大名茶の中心的存在だった片桐石州の流れをくむ石州流や川上不白の流れをくむ不白流が非常に大きな勢力となっていたのです。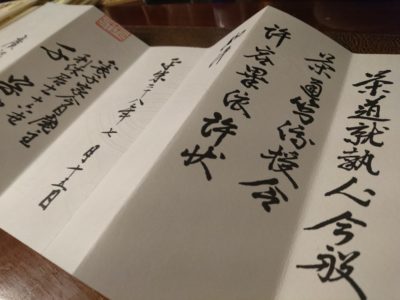 資本力のある企業に顧客が集まるのと同様に、やはり資本力のある大名茶に人々は流れていき、町人茶の代表格だった千家茶道はかなりその規模が小さくなってしまいました。そこで三千家七代が一致団結して町人茶への流れを取り戻すべく本格化させたのが家元制度・許状制度だったのです。
資本力のある企業に顧客が集まるのと同様に、やはり資本力のある大名茶に人々は流れていき、町人茶の代表格だった千家茶道はかなりその規模が小さくなってしまいました。そこで三千家七代が一致団結して町人茶への流れを取り戻すべく本格化させたのが家元制度・許状制度だったのです。
家元制度の仕組みが整ったことで三千家は再び中興し、そのまま時代は幕末へと向かっていきます。
明治政府による文化破壊
 薩長藩士達のクーデターにより江戸幕府は倒幕、明治政府が発足し、西洋かぶれしていた彼らは文明開化と称し、それまで日本を支え続けてきた仏教文化を根絶やしにすべく、抜刀令や廃仏毀釈に手をつけます。仏教文化を根絶やしにするわけですから、仏閣はおよそ三分の二が破壊され、五重塔が家庭用の薪にする目的で跡形も無く解体され、ご本尊たる仏像の多くが焼かれました。法隆寺の仁王像なども焼却炉に入れられ、火がつけられる寸前だったと言います。
薩長藩士達のクーデターにより江戸幕府は倒幕、明治政府が発足し、西洋かぶれしていた彼らは文明開化と称し、それまで日本を支え続けてきた仏教文化を根絶やしにすべく、抜刀令や廃仏毀釈に手をつけます。仏教文化を根絶やしにするわけですから、仏閣はおよそ三分の二が破壊され、五重塔が家庭用の薪にする目的で跡形も無く解体され、ご本尊たる仏像の多くが焼かれました。法隆寺の仁王像なども焼却炉に入れられ、火がつけられる寸前だったと言います。 茶道や華道、香道なども同じ憂き目に遭い、お家取り潰しになりかかったのですが、ここで活躍したのは裏千家11代家元、玄々斎でした。玄々斎は当時の文部大臣にかけあい、「西洋の淑女達を見よ、日本の婦女子達が国際的に評価されるようになるには、西洋の淑女達のような美しい所作や作法が必要である」と説き、茶道三千家のお家取り潰しを免れることに成功します。
茶道や華道、香道なども同じ憂き目に遭い、お家取り潰しになりかかったのですが、ここで活躍したのは裏千家11代家元、玄々斎でした。玄々斎は当時の文部大臣にかけあい、「西洋の淑女達を見よ、日本の婦女子達が国際的に評価されるようになるには、西洋の淑女達のような美しい所作や作法が必要である」と説き、茶道三千家のお家取り潰しを免れることに成功します。
そうしているうちに廃仏毀釈は下火となりますが、元々各大名がパトロンとなっていた大名茶は廃藩置県でことごとく逼塞、茶道三千家のみが時代の流れに乗り生き残りを果たします。その手段こそ、今や「茶道は女性のたしなみ」と解釈されるほどになった、上記の婦女子に茶道を教える風潮です。
裏千家13代圓能斎は京都を拠点としながらも東京にも拠点を置き、様々な財閥のバックアップをもらうために精力的に活動します。それと同時に政府のバックアップを求めるためにも、例えば当時の婦女子教育の教科書たる「女子作法書」に茶の点前を掲載させることに成功し、同時に印刷技術の発展を見た圓能斎は裏千家のテキストを発行しはじめ、それにより点前作法の再統一を本格化させます。
現代茶道の過ち
昭和茶道の功罪
第二次世界大戦の敗戦後、女子茶道の風潮はより一層強まり、「茶華道は嫁入り道具」とまで呼ばれるようになります。当時家元を継いでいた14代淡々斎は昭和15年に淡交会と呼ばれる組織を作っており、戦争が終わったことでそれを本格的に稼働させ、家元の指導を日本全国津々浦々にまで届くような仕組みにしました。その一貫が、淡交テキストと呼ばれる、いわゆる「写真付き教科書」の発行です。 テキストの発行により、都会の富裕層のみならず農村の婦女子にまで茶道の作法が行き渡るようになり、ピーク時は茶道人口が1000万人を超えるなど、茶道人口の大爆発を招きました。淡々斎の跡を継いだ鵬雲斎もまた精力的に茶道の普及に尽力し、今度は国内のみならず、「一盌からピースフルネスを」と標語に、世界平和の実現を目的として世界に茶道を普及させんと尽力します。
テキストの発行により、都会の富裕層のみならず農村の婦女子にまで茶道の作法が行き渡るようになり、ピーク時は茶道人口が1000万人を超えるなど、茶道人口の大爆発を招きました。淡々斎の跡を継いだ鵬雲斎もまた精力的に茶道の普及に尽力し、今度は国内のみならず、「一盌からピースフルネスを」と標語に、世界平和の実現を目的として世界に茶道を普及させんと尽力します。
そうやって茶道人口が爆発的に増えた横で、どうしても避けられないのが質の劣化です。佐々木道誉や一休宗純が現代茶道に与えた影響の存在自体知らない人が圧倒的多数を占めるようになり、「侘び」の感覚すらも身につけないまま、ただ様々な種類の点前を覚えていればそれで良いと言う風潮まで生まれてしまいました。
しかもそんな浅はかな考えを持った人が生徒を持つ事により、茶道の質はさらなる劣化の一途をたどります。今では珠光や利休が励行した「もてなし」としての茶ではなく、単なる習い事、道具集めの茶しか世の中で見ることはありません。散見する「茶道体験」などと言うのもその大半が要領を得ておらず、中には「茶道未経験者でもお茶会体験の講師になれます」と言った、甚だ下劣極まりないサービスまで登場する始末。 茶道人口を爆発的に増やし、多くの職人達に夢と希望を与えたのは昭和以降の茶道界の素晴らしい功績だと言えます。しかしながらその横で質の維持には見事失敗し、中には「本当にこれが家元の言うこと・やることなのか」「この程度の意識や知識しかないレベルでよく家元を名乗れるな」と強い疑問を持たざるを得ない流派すら存在してしまう始末です。人口激増とは、功罪共に併せ持つ物だと言うのがよくわかります。
茶道人口を爆発的に増やし、多くの職人達に夢と希望を与えたのは昭和以降の茶道界の素晴らしい功績だと言えます。しかしながらその横で質の維持には見事失敗し、中には「本当にこれが家元の言うこと・やることなのか」「この程度の意識や知識しかないレベルでよく家元を名乗れるな」と強い疑問を持たざるを得ない流派すら存在してしまう始末です。人口激増とは、功罪共に併せ持つ物だと言うのがよくわかります。
本来あるべき姿
 ここまで長々と茶道の歴史をお話ししましたが、これは歴史の中でも極々ひとつまみ程度を簡単にまとめた程度で、本来ならば本が一体何冊書けるのかわからないほど、多種の歴史にまみれております。そんな茶の世界ですが、たった一つだけ常に一貫しているものがあり、それは「抹茶」と言う存在です。
ここまで長々と茶道の歴史をお話ししましたが、これは歴史の中でも極々ひとつまみ程度を簡単にまとめた程度で、本来ならば本が一体何冊書けるのかわからないほど、多種の歴史にまみれております。そんな茶の世界ですが、たった一つだけ常に一貫しているものがあり、それは「抹茶」と言う存在です。
当たり前と言えば当たり前ですが、「茶道」と名乗る以上は「抹茶の道」なわけですし、すなわち抹茶が美味しくなければ茶道は成り立ちません。質の劣化はその抹茶の味にも浮き彫りになっており、茶道家でありながら茶の味を徹底追究する人はほぼ皆無。みずから茶畑に足を運び、生産者と直接対話をし、時には理想とする茶の味について議論を交わすぐらいの気概のある茶人はほとんど聞いた試しがありません。
質の著しい劣化により、茶道を名乗りながら茶をないがしろにし続けているのもまた、現代茶道の悲しい現実と考えています。だからこそ弊社では、何よりも茶味を限界まで引き出す事を最も大事にしております。
しばしば「心を込めて茶を点てる」などと申しますが、本来は「心」と言う余計なスパイスを排除し、茶の真のポテンシャル(潜在能力)を限界まで引き出す事。そのためにこそ点前作法が存在するのだ、いついかなる時も自由自在に茶の味を引き出す集中力を得るための修行こそが点前作法の、つまり茶道の「道」たる所以なのだ、と弊社では考えております。
茶人CHABITO 代表 小早川宗護

